「ですます調」と「だである調」の違いと使い方
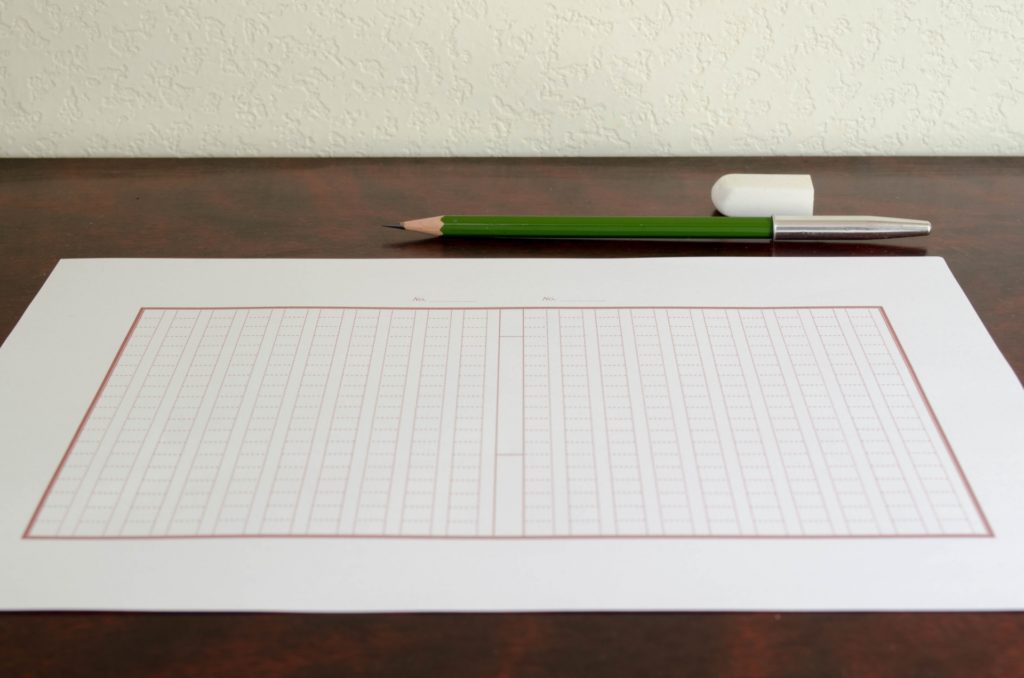
文章を書いていると、文末の表現方法に悩むパターン、よくありますよね。
「ですます調」がいいのか。
はたまた「だである調」がいいのか。
文末の表現方法によっては、そのコンテンツ全体の印象が大きく変わってきます。
それぞれの文体はどう違うのか、どういうときに使ったらいいのか、考えていきます。
目次
ですます調とは
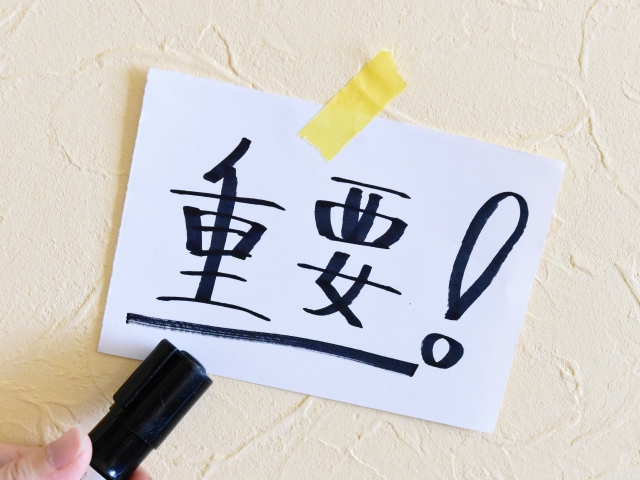
ですます調は、文末を
「~です」
「~ます」
という形で、丁寧語を用いた文章様式のことです。
敬語を使っているので「敬体」と呼ばれます。
いま私が書いている文章も、ですます調です。
相手にやわらかい印象を与える表現ですね。
だである調とは

だである調は、文末が
「~だ」
「~である」
という形で表現した文章様式です。
ですます調とは異なり、敬語ではないのがポイント。
ですます調の「敬体」に対し、「常体」と呼ばれます。
ですます調のメリット・デメリット

ですます調を使うことで、文章全体の印象も異なってきます。
どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
メリット・使うと効果的な場面
ですます調は、先述したように柔らかい印象で丁寧なイメージです。
敬語ということもあり、やさしく親しみやすい雰囲気、品の良さが伺えます。
年齢性別問わず、あらゆるシーンで汎用性が効くといえるでしょう。
たとえば企業のホームページでの解説記事・コラム・商品説明などでは、ですます調がよく使われますね。
デメリット・使わないほうがいい場面
ですます調は柔らかい印象を与える一方、やさしすぎて説得力がある表現にしにくいのが弱点。
また、文末で変化をつけるのが難しいのもポイントです。
体言止めなどをうまく使うなどして、表現に幅を持たせるようにするといいでしょう。
箇条書きなど、端的にまとめたいときにはあまり適していません。
だである調のメリット・デメリット
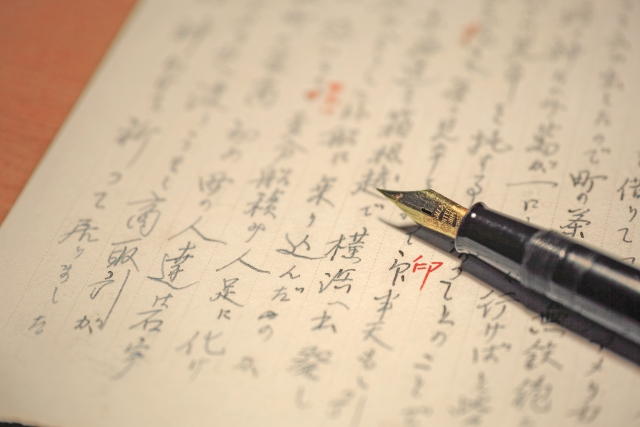
以下では、だである調のメリット・デメリットについて見ていきます。
メリット・使うと効果的な場面
端的・すっきりとまとめたいとき、説得力ある表現にしたいときにおすすめ。
また、「だ・である」以外にも「~と思う」「~だとか」「~らしい」など、ですます調と比較して文末表現が多彩なのもポイントです。
だである調は、箇条書きや論文など、端的に表現したい場合に適しています。
また、レポートや報告書、新聞などでも使用されています。
デメリット・使わないほうがいい場面
だである調は端的に表現したいときに適している一方、断定的できつい印象を与えがち。
使用シーンが論文などということもあり、堅苦しさを感じるのも否めません。
そのため、柔らかい印象に留めておきたい場合にはあまり適切ではないといえます。
WEBコンテンツを作成する際に注意しておきたい使い方

文末表現は、WEBコンテンツの作成時にも大きく影響します。
ここで大きく3つの観点から、WEBコンテンツを作成する際の注意点を見ていきましょう。
コンテンツ内は統一するべし
基本的なことではありますが、ひとつの記事全体を通して、
「ですます調」か「だである調」か、統一しておきましょう。
統一することで、文章全体の違和感がなくなり、すっきりとまとまった印象になります。
文章のなかでどちらの表現も使われていると、
「文章を書きなれていないのかな」
「文章全体を通してもたつきがある」
「なんとなく内容がわかりづらい、読み取りづらい」
というイメージを与えてしまう恐れがあります。
語尾が連続することは避けるべし
たとえば
「……です。……です。…です。」
と、同じ文末が何度も続くのは避けましょう。
こちらも、文章全体が稚拙に見えたり、読みづらく感じられてしまいます。
「……です。そして、……。さらに……でしょう。」
など、体言止めや他の文末もうまく組み合わせることで、文章全体がすっきりと読みやすくなります。
特にWEBコンテンツ作成では、「同じ文末の連続はNG」と校正・編集者からダメ出しされる可能性が高いです。
読みやすさ重視で、いくつかの文末を使って表現を工夫してみましょう。
それぞれのサイトのトンマナに基づいて選択すべし
WEBライターとしてお仕事をいただく場合、それぞれご依頼のサイトに併せた決まりごとが設けられているケースが少なくありません。
そのため、ご依頼内容およびそのサイトのトンマナを確認し、ルールに従って文末表現を選択するようにしましょう。
WEBライティングでは、ですます調が多い傾向にありますが、なかにはだである調でサイト全体を統一しているケースもあります。
執筆後に「NG!!」といわれてしまわないよう、事前に確認してから書き上げると効率もアップします。
シーンに合わせて使い分けてみよう
文末表現を変えてみるだけで、記事全体の印象も大きく変えることができます。
どんな文章を書きたいのか。
どんな風にまとめたいのか。
相手にどんな印象を与えたいのか。
それぞれの用途・シーンに合わせて使い分けてみましょう。







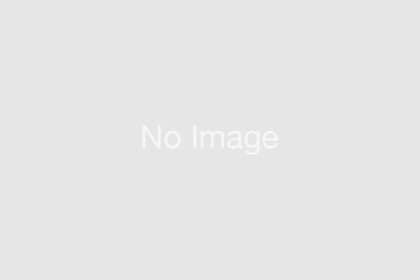




コメントを残す